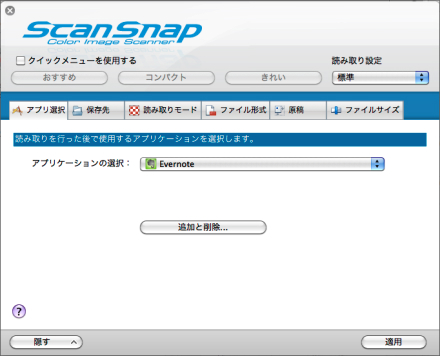本や雑誌を効率よく ScanSnap で読み取りできる様にするには、やっぱりあった方が良さそうな裁断機。
ネットを彷徨っていると、カッターナイフでばらしているは少なくないようですが、結局、裁断機を購入したと言う報告も同様に少なくありません。
さて裁断機というと定番の一つはやはり PK-513L と言うことになりそうですが、価格の面もさることながら、その保管場所も問題になりそうです。
折角、スペースを空けるために書籍の電子化に取り組もうというのに、そのスペースを裁断機のために使うというのでは本末転倒です。
そんなわけでなかなか踏ん切りがつかないところで見つけたのが DC-210N という、ディスクカッター。価格差もあまりありませんので A3 に対応している DC-230N でも良いかもしれません。一応、「Scansnap S1500M」 は A3 を読み込むことが出来ますから。
PK-513L の A3 対応のモデルは PK-511L となりますが、こちらは価格に大きな開きがあるので、選択肢に入れるのは難しいです。
そんなことから、PK-513L と DC-230N を考えています。ここで「迷ったら、高い方」理論を適用しようかとも思いましたが、価格、裁断効率、消耗品、保管場所、安全性と比較すべき項目は多そうです。
| 項目?モデル |
PK-513L |
DC-230N |
| 実売価格 |
3万円強 | × |
約1.5万円 | ○ |
| サイズ |
402x400x170mm
(さらに上方に空間が必要)| × |
360x610x80mm | ○ |
| 重量 |
13kg | × |
3.1kg | ○ |
| 裁断能力 |
約160-180枚 | ○ |
40枚 | × |
| 消耗品 |
替刃(約1.5万円)
刃受(約千円)| × |
替刃(約千円)| ○ |
| 前処理 |
○ |
△ |
| 安全性 |
△ |
○ |
無理矢理、優劣をつけるとこんな感じでしょうか?
消耗品に関してはその交換頻度も考慮に入れる必要があります。ただ替刃だけ見ても価格差が約 15倍ありますから、PK-513L の交換頻度が DC-230N の 15分の1 ということであれば同等と考えられますが、それほど大きな差が出てくるとは考えにくいですよね。
また、裁断能力が 4倍以上異なりますので、1度に裁断できるように書籍を処理する手間が DC-230N の方がかかるということになるので、その点もどう考えるかということも出てくると思います。
そういったことも考えると個人的には DC-230N(または DC-210N)に分があるように思いますが、もうちょっと考えてみようかなっと (^^;;
DC-230N の画像が間違っとるぞ、アマゾン :-p 差し替えられたみたい
楽天で PK-513L を検索する
楽天で DC-230N を検索する